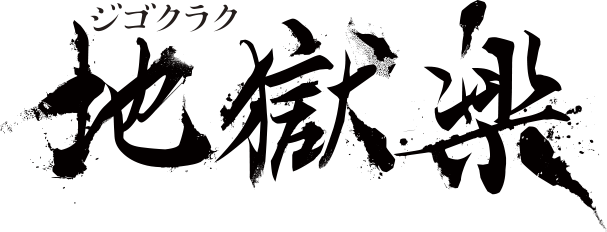

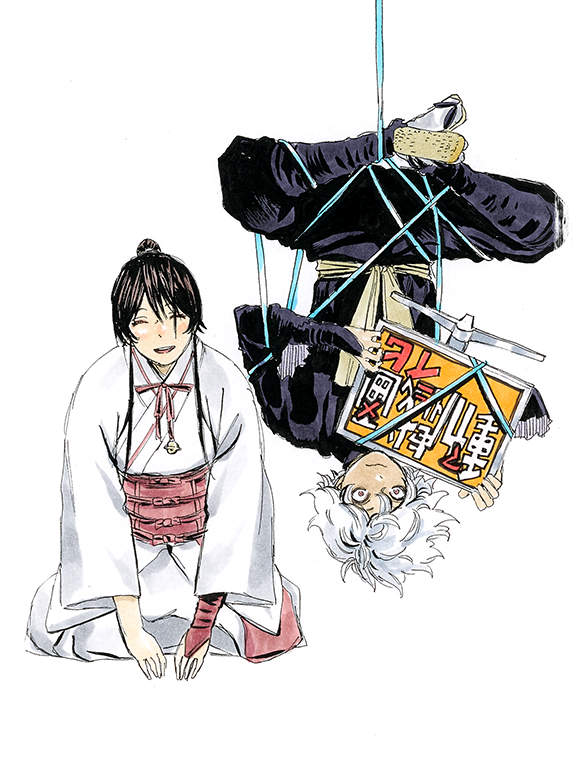

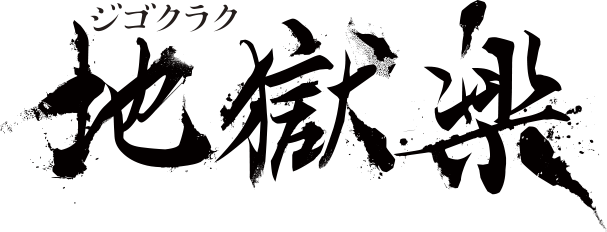

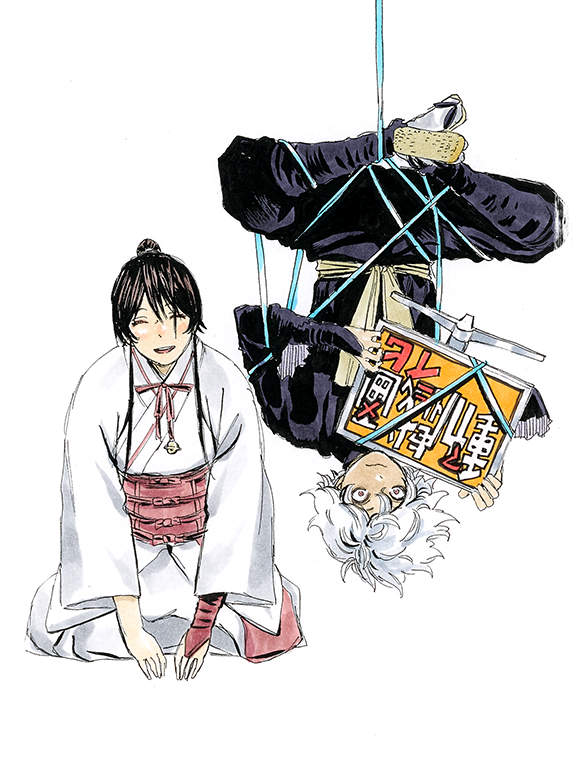

TVアニメ『地獄楽』の放送を記念して、原作者・賀来ゆうじ先生と担当編集・榊原英明さんにお話を伺った。
賀来ゆうじ先生の漫画家としての原点に迫る幼少期・学生時代のお話をはじめ、『地獄楽』誕生秘話や連載中のエピソードを含むロングインタビュー。
この模様は2回に分けて『地獄楽』公式サイトでお届けする。

―― まずは『地獄楽』連載開始当時(2018年)の頃の『少年ジャンプ+』の状況について伺えればと思います。
すでにWebマンガ業界は群雄割拠の時代になっていましたね。業界全体の傾向として、エロ・グロが流行っていたなか、「やっぱりWebマンガにも週刊少年ジャンプに負けないような、ストーリーとして重厚で王道を目指せるマンガがほしいよね」と編集部内で言われていたところに、『地獄楽』が現れたという形でした。
―― 榊原さんが『地獄楽』を担当することになったきっかけを教えて下さい。
賀来先生の前作『FANTASMA』がもともと好きだったので、「ジャンプ+」編集部に新作として持ち込まれた際に、自分が担当したいと真っ先に手を挙げ、連載コンペ用に描かれたネームを拝見しました。
賀来 コンペ用に2話分のネームを作っておいたんです。
第1話は手を付ける必要がまったくありませんでした。2話はちょっとだけ修正していただきましたね。その段階で連載はほぼ決まっていたのですが、編集部からは3話目を見たいという要望があり、新たに3話を作成してもらい改めて会議に回したという流れでした。
賀来 その第3話では、付知や巌鉄斎を出したのですが、「主人公以外のキャラを登場させるには、まだ早すぎる」と言われ、画眉丸の初戦を描き直しました。当初作ったネームは現在の第6話のものになっています。
もっと主人公を描いていきましょうと伝えましたね。群像劇の傾向が結構強かったので。
賀来 その指摘は連載の最後まで言われ続けました(苦笑)。僕は割と全体を見渡して考えるタイプなので、群像劇に振りすぎてしまう傾向があるんですよね。榊原さんには「ちゃんと画眉丸視点に戻しましょう」と、定期的に言われていました。
たしかに最初はそこが懸念点ではありましたが、各キャラクターの立て方が想像以上に上手く、それが魅力につながっていきそうだなと思いました。
―― 先ほど、「ストーリーとして重厚で王道を目指せるマンガ」とありましたが、どういったところを意識してお描きになるのでしょうか?
賀来 それは僕に限らずだと思うのですが、作家自身は描く時にあまり意識していないような気がします。王道を作ろうと思って王道作品になるというよりも、道からはみ出そうと思っていたものが、結果的に王道として認められていく。逆に、王道を意識すると、かえってあまり上手く行かないのではないかと、僕は思います。自分としては好きなものをひたすら描くだけですね。
―― 賀来先生の『FANTASMA』は月刊誌『ジャンプSQ.』の連載でした。『地獄楽』が初の週刊連載でしたが、テンポ感やストーリーテリングにおいて、どんな違いがありましたか?
賀来 連載当初から榊原さんがおっしゃっていたのは、1話分の19ページを毎週描くことになるので、そのなかで起承転結のドラマをカッチリ作ることは難しいということでした。それよりも、感覚的にパッと分かりやすい、たとえば格好良いとか、かわいいといった目を引くような起点を1個がっちり作って、そこに全集中してテンポよく読めるように作っていくことが大事だと。僕は結構ドラマを作ろうとしてしまうタイプで、月刊誌の45ページに慣れていたので、「週刊連載においては、ドラマは何話分か使って作るつもりでやった方がいいですよ」という話はよくされました。そこは後半になっても割と意識しながら続けていた感じではあります。
―― 紙の誌面からWebの画面になったことで、画的な見せ方は変わりましたか?
賀来 そこも榊原さんから教わりました。ほとんどの人がスマホで見るので、吹き出しと文字は大きくする必要がありますし、スマホは基本的に1ページずつしか画面に出ず、紙の要領で見開き演出を使いすぎると、勝手が違って見えてしまうので、あまり多用しないよう意識しました。初期の頃は見開きを使うときも、片方のページだけ見ても流れとして違和感がないような使い方をしていましたね。
―― たとえばキメのページでは縦構図にするとか?
賀来 そうですね。やっぱり1枚構図を意識していました。Webマンガでなかったら、見開きにしていた場面も多かったかもしれないですね。
賀来先生は紙とWebの両方を経験した身として、どちらがやりやすいとかありました?
賀来 正直、どちらでも関係ないかなぁ……。完結したあとで振り返ると、もちろんある程度は大事なことだとは思うんですけど、そこまで徹底して意識しなくてもよかったかなとも思います。それに、現在では読者のほうも色んな意味でWebマンガにだいぶ慣れてきていそうですし。
―― 見開きではありませんが、バトルが始まったページをめくった途端、いきなり決着が1枚絵で表現されている演出がありました。
賀来 そのあたりの演出はWebマンガだから意識していたところでしたね。やっぱりインパクト重視ですから、めくったときにビックリするように。バトルの省略以外のときにも使っていた手法ではあります。

―― やっぱり「ジャンプ+」という媒体であったことは、『地獄楽』において決して無視できない要素のようですね。
賀来 そうですね。この作品に限らず、どこにどの形で載るか、媒体は作品作りをする上での大きな要因だと思います。『地獄楽』にとってはやっぱり「ジャンプ+」というメディアが一番合っていたんだろうなと、完結してから改めて思いますね。

―― 先ほど、榊原さんは「キャラクターが立っている」とおっしゃいましたが、賀来先生は連載を始めるにあたって、最初にどのぐらいのキャラクターを用意されていたのでしょうか?
賀来 『地獄楽』は2話目で、浅ェ門以外はほとんどすべてのキャラクターを出しています。物語全体の半分くらいまでに登場する主要キャラクターは最初から作っていました。天仙も、デザインこそ登場する場で作る部分もありはしましたが、設定自体は1、2話のネームの段階ですでに決まっていた感じですね。
―― ストーリー上でキャラクターたちがどう生き、どう死んで行くかという行く末はどの程度考えられていましたか?
賀来 ストーリー展開みたいなものは敢えて決めずにいました。というのも、僕自身が彼らの生き死にに驚かないと、きっと読者を驚かせることもできないだろうと思ったんです。ただ、基本的に全キャラクターに対して、生き残る可能性と、死ぬ可能性の両方を考えてはいました。そこからは本当に成り行きです。話の流れ上、「ここで生き残ってしまったらご都合主義になるな」と思ったら、躊躇なく死のカードを切るようにしていました。僕自身が話の流れに身を任せていたので、当然榊原さんにもお伝えしておらず、ネームを提出したときにそれを知るという状態でした。
「新鮮な反応がほしいから」と先生に言われていたので、僕も聞かないようにしていました。直近1巻ぶんぐらいの全体の流れは事前に聞きつつも、細かな内容は各話で打ち合わせるという形でしたね。
―― たとえば、このキャラクターは人気があるから、死なせないでくださいみたいなことはありませんでしたか?
賀来 やめましょうみたいな話は別になかったですね。非常にやりやすい環境で好きなように作らせていただきました。
やっぱりこの作品の魅力のひとつは、キャラクターの死に際にあると思うので、格好良く最期を描いてくれれば、それで本望だなと思っていました。
―― 賀来先生はキャラクターの最期を描いている時に感情がこみ上げてくるような経験はありましたか?
賀来 あります、あります。ネームのときはテンポを考えていたり、読者や榊原さんの反応を期待して描いていくので、そこまで死を実感することはないのですが、OKが出てペン入れをするときになると、ちょっと違います。死の確信を持った上で、そのキャラクターの指先だったりシワだったりといったディティールをじっくりじっくり描いていくと、どうしてもその人物に寄り添っていく気持ちになって、「ああ……、このキャラクターは死んでしまうんだな」とか、「なんてかわいそうに……」と、しんどいなと思うことは何度もありました。
―― 具体的に誰か聞いてもいいですか?
賀来 やっぱり典坐ですね。でも、僕が悲しまないと読者もそう思ってくれないから。読者を追い込むことが、イコール自分を追い込むことだと思って、そこはもう切り離して、徹底的にかわいそうに思ってもらうように描いていました。

―― 個人的には、デザイン的にも主役級の格好良さだった衛善が、思いのほか早くに退場したことに驚きました。
連載時の読者の反応でもそうした感想は多かったですね。
賀来 あぁ……。でも彼だけは当初から早くに退場することが規定路線でした。僕は罪人と浅ェ門をツーマンセル(2人1組)で考えているのですが、陸郎太というキャラクターを作った段階で、そのお付きの人は死ぬことが確定していました。というよりも、殺すことで陸郎太のキャラが立つだろうと考えていました。それを誰にするか。せっかくだから一番強そうな打ち首執行人にしようと考え、彼に決めたという経緯です。これは余談ですが、アシスタントさんにも伝えていなくて、衛善が登場したときから「試一刀流一位って、超強そうですよね!」と活躍を期待していたので、いざその場面の原稿を渡した時に、とてもびっくりしていました(笑)。
―― 罪人と浅ェ門をセットで考えていたというお話を、もう少しお聞かせください。この組み合わせはどのように考えましたか?
賀来 罪人のキャラクターを先に考えて、それに合う浅ェ門は誰がいいかなと選んだこともありましたし、その逆もありました。たとえば典坐の場合は、熱くて志の高い人物像を先に作って、彼を一番燃え上がらせるのはどんな罪人かと考えました。それは無罪の人だろうと思い、ヌルガイをあてていきました。杠と仙汰のケースでは、杠という自由奔放でジョーカーのように動く人物を先に考えて、それであれば正反対の性格で四角四面な人物のほうが困って面白いだろうと、あてがった形です。ペアごとに作り方はそれぞれですね。
―― 人間関係はどの程度考えられていたんですか?
賀来 先ほどの話に通じるところではありますが、やはり週刊連載なので、あまりカッチリ用意しても使えなかったりしますし、作り込みすぎても想定外のことが起きた時に崩れやすくなる心配があります。ですので、核だけはほぼ全キャラクター決めておいて、あとは流動的に作っていくようにしました。兄弟弟子とか上下関係の部分の関係性は事前にありつつも、仲良しの度合いなどは物語を進めるなかで生まれていったものでした。
―― 人物の内面がキャラクターのデザインに反映されるというお話が前回のインタビューでありましたが、特に強く表れている人物は誰でしょうか?
賀来 どのキャラクターのデザインも、自分が気に入るまで練りに練ったつもりですが、一番印象深いのはやはり浅ェ門の殊現(※コミックス4巻より登場)ですね。彼は罪人を絶対に許さない人物で、企画の最初期から考えていました。すごく強烈なキャラクターを持っているので、なかなかそれに見合うデザインを考えるのが難しかったです。当初は年齢がもうちょっと高いキャラクターで、この人の怖さや威厳みたいなものを意識していたと思うのですが、紆余曲折あって、現在の見た目を思いつきました。僕の中では主人公みたいな見た目にしたつもりです。これも余談ですが、アシスタントさんが名前を知らなかった頃に、彼をコードネーム・桃太郎と呼んでいて(笑)。あぁ、主人公っぽく見えてるんだと安心した覚えがあります(笑)。
初登場のとき、「ジャンプ+」の細野編集長にも「彼は人気が出そうだね」と言われたのを覚えています。キャラクターの内面でいうと、やっぱり画眉丸は賀来先生そのものだと思うんですよ。
賀来 本当ですか!? 僕、こんなに“がらんどう”じゃないですよ(笑)。
いやいや、真面目な性格とか。
賀来 でも確かに、藤本タツキ先生とか龍幸伸先生とお話していても、僕の性格のどこかしらがキャラクターに詰まっていると言われますね。藤本先生には士遠だと、龍先生からは亜左弔兵衛だと。僕自身はあまり意識してはいないのですが、いろんな方にそれぞれのキャラクターで言われると、そうなのかもなと。

―― 描いていて苦しかったり、許せないと思ったキャラクターはいましたか?
賀来 デザインが面倒くさいので、早く退場してくれないかなと思うことはありました(笑)。でも内面の部分に対して、そう思うことはありませんね。それも作品のテーマではあると思うのですが、その人にはその人なりの事情や考え方があって、行動が悪く見えたり逆に良い人に見えたりするのも、ある立場からの見方でしかない。話の流れ上、退場させてしまったけれども、別の流れがあればもっと生かして膨らませたかったなというキャラクターは大勢います。
コミックスを隅々まで読んでもらうと分かりますが、早めに退場したちょっとしたキャラもおまけ漫画でちょっと出てきたり、回想シーンに出てきたりとか、先生のキャラクターへの愛は誰に対しても非常に行き届いていますね。
賀来 茂籠牧耶というキャラクターは背景がしっかりしていたのですが、本編であまり活躍できなかったので、小説(『地獄楽 うたかたの夢』)になるときに、菱川さかくさんに設定をお渡して、「実はこんなやつなんです」とお伝えしたところ、上手く拾って使っていただけて嬉しかったですね。
嫌われ者でいうと、徳川将軍ぐらいかな?
賀来 そうですね!(笑)。内面がないですからね。そういうキャラクターを作って悪を担わせてしまった感じがして、作り手からすればちょっと申し訳ない感じがします。
―― 天仙たちはどんなふうに作り上げたキャラクターですか?
賀来 他のキャラクターと同じように作っていった感じですね。
そうですね。ネームの返事で、「こっちの方向には行って欲しくないです」ってことをサラッと言ったぐらいで、他に覚えてるのは「何でもありはナシにしましょう」というくらい。
賀来 言われましたね。超能力の限度、例えば瞬間移動はしないとか、そこまでファンタジーなことはできないということを2人で話し合って、設定上の幅みたいなものは決めていきましたね。
あとはそんなに大きくしすぎないようにしましょうとか。
賀来 怪獣バトルみたいになっちゃうと、分からなくなっちゃうから。
サイズが大きいと読者から遠いお話になっちゃいますしね。
―― 前回のインタビューで、キャラクターが独り歩きしたというお話を伺いました。『地獄楽』でそれを感じたのはどのタイミングでしたか?
賀来 僕の想定を超えたという意味で言うと、典坐の死がそれでしたね。士遠、典坐、ヌルガイの3人になった時に、男のうちどちらかが死んで1人がヌルガイを守るという流れになっていったんです。それでネームを描いていたら、意外とすんなり行ってそれを榊原さんに出したら……。
最高の最期でした。
賀来 と、言われたんです。彼の最期は僕の想定以上に早かったですね。自分でも驚いたからこそ、読者の方も意外に思ってくれるんじゃないのかと感じました。
―― 連載中、特に大変だったことは何でしたか?
賀来 基本的に榊原さんは僕がやりたいことを優先してくれたり、寄り添ってくれる編集者さんだったので、僕自身は好き放題やらせてもらった記憶ばかりです。ただ1回だけ、画眉丸と朱槿が初対決する回は、全体としてもっとバトルを盛り上げてほしいっていう話をされたのですが、作画に入るギリギリのスケジュールだったんです。正直、このタイミングでのネーム全替えはキツイなと思ったのですが、夜通しで19ページ差し替えて送ったら、「すごく良くなりました」と言ったあと、「僕自身もこのタイミングで全替えを申し出るのには、すごく勇気が要りましたが、言ってよかったです」と。僕は各話のアオリ(冒頭と次回予告の文言)を気にする方なのですが、その回はアオリも冴えていましたね。連載中でネームの直しを指摘されなかったのは3回か4回くらいでしたかね。
そうですね。

―― 逆に言えばそれだけしかなくて、他は大小どこかしら指摘が入っていたんですね。
賀来 そうですね。僕が何かしら言ってもらいたいんです。それで「強いて言えば……」と挙げてもらいます。それでもなかったのが3〜4回。僕自身が微妙だなと思いながら出したものは、読まれたあとやっぱり「ここちょっと微妙じゃないですか」と言われることもありました。僕は榊原さんをスーパー読者と思っているんです。僕の目の前に1人でも違和感を持つ人がいたら、実際の読者はその何倍もいるわけですから、その指摘はどんなことであっても、自分のためになるわけです。もちろん、それを受けてどのくらい変えるのかの程度は差があります。セリフのちょっとした変更から、先ほどのように根本から変えるまで大小ありますが、作品を良くしようと思って指摘してくださるので、言われたことは必ず直すようにしていました。直さなかったことはありません。
そうでしたね。必ずこちらの意図を汲んでくれて、さらに面白いものがいつも上がってきたので、読んでいてとても楽しかったです。
―― 榊原さんが賀来先生に伝える時に、言い方とか大切にしてることは何ですか?
そうですね……、読んだものに対する違和感を具体的に言葉で説明するようにはしています。
―― 「なんとなく、よくないんだよね」ではなく。
はい。直感的な言い方はしないようにします。僕が「引っかかるな」と思ったのであれば、それはどこに要因があるのか、「ここですかね?」と、一緒に答えを探すような感じですかね。
賀来 僕も新人さんとかアシスタントさんから、「自分の読み切り用のネーム読んでもらえませんか?」と意見を求められることがあるのですが、ハッキリと違和感の正体を言葉にできることって、実は少ないんです。伝えてはみるものの、本当にそこを直したら良くなるのか、自分自身でも確証を持って伝えられているわけではないと思うんです。だから、榊原さんから何か指摘があったとしても、1つの違和感が表に出てきただけで、根っことか本当の違和感の要因は、もしかしたら別にあるのかもしれない。なので、何かの指摘があったとしても、それをそのまま直すのではなく、ちょっと雑談を重ねて、本当の違和感はどこにあるんだろうと探すようにしています。そうやって話し合いながら、最初はここに違和感があったと思ってスタートしたけれども、結局別のところに原因を発見するなんてこともあります。
自分が読み違えてた部分があるかもしれないし、だったらこうした方が分かりやすいですよね……と、打ち合わせを重ねていくわけです。
賀来 そういうコミュニケーションが大事だなと、常々思います。

―― さて、『地獄楽』のTVアニメ化について、原作者としては率直にどんな思いですか?
賀来 もちろん嬉しいですし、やっぱりスゴいなと思っちゃいますね。僕はアニメーションがものすごく大好きですし、アニメーターの本を読んだりして、アニメ的な手法を何とかマンガの中に落とし込めないかなと、研究したり取り入れたりするのが好きなんです。そんなわけで、映像を見ると、まだちょっと実感が湧かない感じというか。あまりにも圧倒されてしまって、現実的ではない感じを覚えるほどです。
―― 特にどんなところにスゴさを感じましたか?
賀来 特に音の部分ですね。劇伴、SE、声の芝居……。マンガを描く上で、例えば嬉しいシーンを描いたとします。でもニュアンスって、やっぱ一つに固まらないと思うんですね。そこには別の角度で見ると寂しさも含まれていたりする。ただ、少年マンガとして読者に伝えるとなると、その要素を絞って描く必要がどうしても出てきます。それをアニメーション作品では音を使うことで、そのあたりのニュアンスも言外に、あまり主張しない形で通底させることができます。拝見して、こんなに表現ができるんだなと、圧倒されました。
―― アニメ化をする上で、特に天仙の設定が大変そうだなと思ったのですが、お二人で連載中に「アニメ化したら……」みたいな話題は出ましたか?
話しましたね。「アニメになったときにどうするんですか」って話をしたら、「なるようになるんじゃないですか」って(笑)。

賀来 無責任にも(笑)。良くも悪くもアニメになったらどうしようなんて考えないですし、僕は原作者ですが、アニメ『地獄楽』は別の作品ぐらいのつもりでいるので。例えば、ある程度設定が変わったり、アニメ用に改変することがあったとしても、『地獄楽』をよくするための志のもとにあって、それでアニメ制作側がモチベーション高く行えるのであれば、それで良いと思います。実際のアニメ制作でも、天仙を描くにあたって僕が心配したことも、何か言われて困ったこともありませんでした。
―― 牧田佳織監督とは何かお話をされましたか?
賀来 はい。牧田監督は、最初に賀来ゆうじのことを女性作家のペンネームだと思われていたそうなんです(笑)。それは作風が女性っぽいからだと。他の方にもたまにそういったことを言われたりもします。それと関係しているか分かりませんが、佐切のキャラクター性について監督とお話をさせていただいた際にも、いわゆる解釈がピタリと一致して、僕がこういうふうに描きたいとか、思いを込めていることについて、ことさら言葉を尽くして説明をしなくても汲み取っていただけた感覚を覚えました。そこがとてもありがたかったですし、こちらが伝えたかったことは誌面を通じて伝わっている確信を持てました。
―― 最後に、原作から応援してくださっているファン、そしてアニメで初めて『地獄楽』に触れたファンの皆様へのメッセージを賀来先生よりお願いいたします。
賀来 一度、アニメスタッフの皆様とお話をさせていただく機会があり、その時に「この方達が作ってくれるなら信頼できる」と思いました。今は一視聴者の立場で毎話楽しませてもらっています。見返す中で、舞台は江戸時代末期だし、また原作も少し前に完結済みではあるけれど、今現在に通じる部分のある作品だと改めて思いました。そう思わせて下さったアニメスタッフの皆様に改めて感謝したいです。是非、アニメで初めてこの作品に触れる方も、そうでない方も、キャラクターを応援する気持ちで見てみてください。きっと誰かしら、貴方の今現在に通じるキャラクターがいるはずです。そうであれば原作者として幸せです。